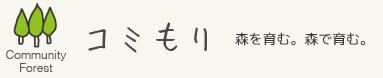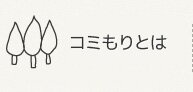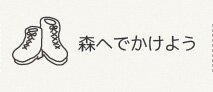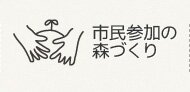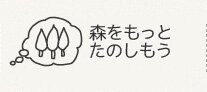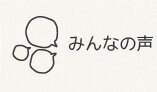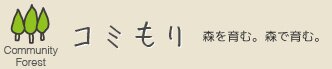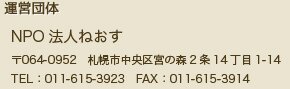体験プログラムに参加した方や、コミュニティーフォレストリーに関わるスタッフの生の声をお届けしています。
みんながそれぞれの立場、それぞれの方法で森に関わることで、心の中に小さな気づきの芽が生まれています。
そのたくさんの小さな芽がいつか大きくなって、一つの森ができあがる。コミュニティーフォレストリーはそんな想いでプロジェクトを推進していきます。

川口一幸 さん
川口 一幸さん(62歳)
森づくりボランティア団体代表
(脳梗塞で倒れるも、復活を果たし、少しずつ森づくり活動に再チャレンジ)
コンテナ設置や木道などのお手伝いをさせていただきましたが、森や道づくりのスペシャリストの話は奥が深くて聴いていて楽しいですよ!
温暖化防止に貢献したい、森づくりをしたい、明日への鋭気を養いたい、森の恵みをいただきたいなど、森はいろいろな要望をかなえてくれるところだと思います。

佐々木裕明 さん
佐々木裕明さん(47歳)
元道庁森作り担当
森での活動は、植樹などの本格的な森づくりはもちろん、森の探検、どんぐり拾い、ハスカップ狩り、木道づくり、野草団子づくりなどなど、アイディアたっぷりの活動に気軽にチャレンジすることができます。
そして何より、たのもしいスタッフや森の賢者たちが家族のようにサポートしてくれるので、子どもからおじいちゃんおばあちゃん、車いすユーザーの方なども安心して参加できます。うれしいですね。
前回参加した時、赤ちゃん2人を乳母車に乗せ、ニコニコ笑いながら森を散歩しているおばあちゃん?に出会いました。嬉しいシーンでした。

三上千佳子 さん
三上千佳子さん(44歳)
まちづくりNPO
植樹祭の時に、いつか、この植えた木が大きくなる頃に、いっぺん森を見たいと思っていたの。
10年先位かと思っていたら、案外早くにチャンスが巡ってきてね。森には「和みの森」なんて、名前がついて、和みの森運営協議会が出来て、いろんな方々が市民の森にしようと手入れを始めたって。 木を植えるっていうし、これは是非一度、イベントにして、みんなで行かなきゃねって思ったから、早速行ったの。
植樹祭の時に植えなかった、補欠の木を皆で植えて、森を歩いて・・・車イスの通れる木道を作るっていうじゃない。
コンテナハウスも設置するって。どんどん「森のコミュニティーセンター」らしくなってくるわねぇ。

北川陽稔 さん
北川陽稔 さん(32歳)
映像クリエイター
「和みの森」そして「つた森山林」の風景は、人々が自然に集い、森から「パワー」をもらって帰る場所…という印象でした。
苫東の森の中心にある、開けた開放的な空間は人をひきつける何かがあるような気がします。それはもしかしたら、原始の時代から人の心の奥底にあり、都会に住む私たちが、普段は忘れてしまっている、意識の深いところにある感覚なのかもしれません。
例えばいつか、この広大な森の中に開けた憩いの場で、月夜に人々が集い、火を焚いて一夜を過ごすようなイベントがあればぜひ参加してみたいです。
炎を囲みながらダンスを踊ったり、普段は話せないようなことも真剣に語り合ったり…。
もしビデオカメラを持ってその場に居合わせたなら、それだけで一本のドキュメンタリー映画が撮れそうな気がします。

近藤理恵 さん
近藤理恵 さん(43歳)
参加者(小学校2年生のお母さん)
もともと自然の中で遊ぶのが子供以上に大好きな私。
子供と一緒に自由に安全に遊べる場所はないのかなぁと思っていました。そんな時、和みの森の活動を知ってワクワクした気持ちで参加しました。
もちろん知り合いは全然いませんでしたが、森の中では不思議と自然な会話ができます。そして毎回いろいろな専門の方が来て普段経験できないことを教えてもらえます。 その時期にとれるハスカップや野いちご、山ぶどうなどの森の恵みを味わえるのも魅力ですね。
外遊びがちょっぴり苦手な夫も少しずつその魅力にはまってきているようです。 私にとって和みの森は大人も子供に帰って自由に遊べる、そして贅沢で有意義な時間を過ごせる大切な場所です。

相原万弥 さん
相原万弥 さん(30歳)
正直、アウトドアが嫌いな私はパワースポットに興味も無く、森へ行くなど考えただけで熱が出そうな感じでした。
こんな私が主人に付き合い渋々森へへ行く事となり、まさにパワーゼロのまま初めて森へ足を踏み入れました。
イベントの後、直ぐにでも帰宅したいと思っていたのに「森を散歩する」事となり、またまたパワーゼロでした。しかし、初めて森を散歩して今までとは何かが違う気持ち良さ、心地良さを感じる事ができたのです。
ただ森を散歩しているだけなのに何?どうして苦手な森が気持いいの?もしかして、ここパワースポット?そして一番ビックリしたのは、「またここに来たい」と思った自分自身に驚きました。
その後は「月に一度は森作り」に参加し、色々な方と木道作りをしたり森の惠を頂いたりとアウトドア大好きになりました。キャンプへ行ってもテントで寝る事ができず、いつもバンガローで寝ていた私が今ではテントも好きになったのです。
アウトドア好きになった私を一番喜んでくれたのは主人でした。夫婦円満パワースポットかも?
私は「和みの森」から、たくさんのパワーを貰っています。
自然の力って本当に素晴らしく、パワーを頂いたお礼に何かしたいと思う様になりました。これからも、色々な方と楽しく森作りをしていきたいです。

高橋早苗 さん
高橋早苗 さん(34歳)
夫の転勤で苫小牧に来ました。別に本とかを読んだわけじゃないけど、とにかく子どもたちを野山で育てたいとずっと思っていたんです。
それは、自分が農家で育ったからかもしれませんが。で、友達とかいたわけではないけど、たった一人で森づくりの活動にエイヤって飛び込みました。
そしたら、そこに思った通りのシーンが広がってました。そうそう、こんな感じ、っていうところでしょうか。
子どもたちも、「森でのあそびはつかれるけど面白い」といいます。
森での活動がきっかけで、私はお友達がいっぱいできたのは言うまでもなく、ですね。

井筒弘子 さん
井筒弘子 さん(42歳)
私はただ 外遊びが 好きなんだと思います。
自分が子供のころは 苫小牧の中心部でも空き地があって、砂利道で木や草もたくさん生えていて、毎日近所の子供達と遊んでいました。
自分の子供にも やっぱり元気に外遊びしてもらいたい。そんな思いでいたところにいろいろな出会いと偶然があり、和みの森に出かけています。
うちの子供達は 森の中では のこぎりで木を切る時や 木の実を探す時に普段の様子からは考えられない集中力を見せてくれます。
そんな姿をみると いつもは家では 小言ばかりなんだけれど『まあいいか…』という気持ちになります。
私自身も 仕事、家事、子供達にことで 凝り固まっている毎日ですが、森に行くといろんな方たちがいていろんな話を聞かせてもらったり聞いてもらったりすることで、心の中のモヤモヤが 『まあいいか…』に なっていくんですよね。
この『まあいいか…』に 私達親子は救われているのかも知れませんね。

上田融 さん
上田融 さん(37歳)
いぶり自然学校、苫東和みの森運営協議会 事務局
そうなのです。自分でもなんだかおかしいのです。
ぼくの本業は「子どもキャンプディレクター」です。子どもたちを自然の中で遊ばせることが「うえだんな」の真骨頂であり、そっち系の技術と経験は、ちょっと自信があります。
が、「この木は切ったほうがいい」「この木はだめ」とか、そんな木こりのような経験はゼロに等しく、ましてや「事務局」だなんて数字を見る仕事は最も苦手。
数字を見るぐらいなら、まだ蚊のいる森の中にいたほうがマシです。 そんな奴がなぜか今、「森づくり」と名のつく本を読み倒し、森づくり研修会に出まくり、チェーンソーの目立てに萌え、そびえる木を見上げては、「う?む、この木はいい…。」とか分かったようなことを言ってるんですね。
なんでそうなったんだろう?そんなキャラを目指し始めたきっかけは何だったんだろう?
…まあ、いろんなタイミングがあったのですが、やはり一番大きかったのは、自分が今までやってきた子どものキャンプで大切にしてきたことと、森づくりで大切なことが一緒だと気づいたことですね。
「子どもキャンプ」も「森づくり」も、自分と、その周りの環境、あるいは関係を幸せにするよい方法なのです。
それに気がついたら、あとは早かったなあ。たまにはメゲルこともありますが、とても前向きに事務局作業に従事しています。
さあ、今度はどんなおもしろいことをやろうか?あれとあれをくっつけたら、面白い化学反応が起きそうだ!
あの人とあの人との出会いも面白そうだな…。
森から帰った後は、いつもそんな物思いにふけっています。

相原正雄 さん
相原正雄 さん(43歳)
苫東和みの森運営協議会 会長、車椅子ユーザー
まだ木道が出来ていない先へも皆さんとコンパネの力をお借りして、普段は行く事が出来ない所まで進む事が出来とても気分爽快でした。
ここをこんな風にして、あそこはあんな風にしてと、皆さんと森づくりのお話も楽しいです。
私の中でもあんな風になればいいなぁ〜と妄想を膨らませています。少年の頃に描いた夢の様な機密基地がもしかしたら・・・・・。
自然の恵みを頂き、皆さんと一緒にその場で作り!食べる!今後も想像しただけで楽しく、とても楽しみでなりません♪

高野克也 さん
高野克也 さん(32歳)
大雪山自然学校:ニセウの森づくりプロジェクト担当
はじめは森づくりとは何だろうと思っていたんだけど、いろんな人と森の中に出かけていって思いました。 森は豊かなコミュニケーションツールであると。
森はひとりでに語りかけてきます、時に雄弁に、時に寡黙に。
私たちはその声や動作を感じ、森を活用しながら様々なコミュニケーションでつながることができるのです。
子どもたちと森に入る時も大人たちと森に入る時も目の輝きはみんな同じです。森の中での驚きと出会いを楽しみにしています。
自分も気づけば今日はどんな新しい発見があるかな?と期待しています。それは森と一緒に活動する参加者の両方に対してです。
さて今日はどんな人とどんな森に出かけようかな?考えるだけでワクワクします。